猛暑が続く昨今ですが、最近、ぐっすり眠れていますか?
「夜中に何度も目が覚める」「寝つきが悪い」「朝すっきりしない」そんな声がよく聞かれます。
睡眠の質が高まると、体も心も自然と元気になり、毎日の生活がぐっと過ごしやすくなります。
また、実は認知症の人にとっても、睡眠はとても大事なんです。
今回は睡眠の質を高めるための工夫についてまとめてみました。
睡眠の大切さ
睡眠は、生活リズムを整え、
- 免疫力を維持する
- 認知機能を安定させる
- 気分を安定させる
ために欠かせません。しかし、加齢とともに眠りが浅くなり、中途覚醒や早朝覚醒が増える傾向があります。「長く眠る」よりも「質の良い眠り」を大切にするという視点で考えてみましょう。
睡眠の質を下げる要因
☑ 日中の活動量が少ない
☑ 昼寝が長すぎる
☑ 夕方以降のカフェイン・アルコール摂取
☑ 寝室の温度・湿度が快適でない
☑ 不安やストレスが強い
当てはまるものが多い場合は、生活を見直す必要があります。
睡眠の質を高める生活習慣
次のポイントを心がけましょう。
☑ 朝の光を浴びる(体内時計をリセット)
☑ 日中に軽い運動を取り入れる(散歩・体操など)
☑ 昼寝は20〜30分まで
☑ 午後以降のカフェイン(コーヒー・緑茶)を控える
☑ 寝酒を避ける(アルコールは眠りを浅くする)
☑ 就寝前にリラックスタイムを持つ(音楽・読書・ストレッチ)
睡眠環境を整える工夫
快適な寝室作りも重要です。
☑ 室温:夏は25〜27℃、冬は18〜22℃が目安
☑ 湿度:50〜60%程度
☑ 季節に合った寝具を使用する
☑ 枕や布団は体に合ったものを選ぶ
☑ 照明は暗めに、音は静かに
介護者ができるサポート
カランとしての支援は以下の通りです。
☑ 規則正しい生活リズムを意識する
☑ 安心できる声かけや環境づくりを心がける
☑ 不眠や日中の強い眠気が続く場合は医師に相談する(服薬する場合は様子をしっかりと観察し、医師にフィードバックする)
🌙 質の良い睡眠のためにできること
1. 就寝前のリラックス方法
眠りに入りやすい心身の状態を作ることが大切です。
心と体をゆるめる工夫
- 深呼吸:4秒吸って、6秒吐く呼吸法で副交感神経を優位に。
- 軽いストレッチ:首・肩・足首を回す程度。血流を良くして緊張をほぐす。
- 入浴:就寝1〜2時間前にぬるめ(38〜40℃)のお風呂に入ると寝つきが良くなる。
- アロマ:ラベンダーやカモミールはリラックス効果あり。
- 音楽:静かなクラシックや環境音(小川のせせらぎなど)も効果的。
デジタルデトックス
- 就寝前1時間はスマホやテレビを控える(ブルーライトが脳を覚醒させるため)。
睡眠によい食べ物・飲み物
🍴 食べ物(眠りをサポートする栄養素)
- トリプトファンを含む食品
(大豆製品、牛乳、チーズ、卵、バナナ、ナッツ類)
→ セロトニンを作り、夜にメラトニンへ変化し眠りを助ける。 - ビタミンB6を含む食品
(鮭、サンマ、鶏むね肉、バナナ、玄米)
→ トリプトファンからセロトニンを作るのを助ける。 - マグネシウムを含む食品
(ほうれん草、アーモンド、海藻、豆類)
→ 筋肉をゆるめ、リラックス効果。 - 消化のよい食事
→ 就寝直前に油っこいものや大量の食事は避ける。
⚠️また、お腹が空いた状態も睡眠の質が下がりますので、夕食と寝る時間が空いてしまった場合は、バナナをよく噛んで食べることがおすすめです。
⚠️「よく噛むこと」も、セロトニンの分泌を促すことができます。また、消化が楽になるので胃腸の働きを助けます。「ありがとうございます(10文字)」を3回唱えながら噛むと30回噛めます。ぜひ習慣にしましょう。慣れるまでは最初の一口からでもOKです。
☕ 飲み物
- ホットミルク:トリプトファンと温かさでリラックス。
- カモミールティー:安眠ハーブとして有名。
- ルイボスティー:ノンカフェインで抗酸化作用もあり。
⚠️カフェイン(コーヒー、緑茶、紅茶、コーラ、チョコレートなど)は午後以降は控えめに。
まとめ
睡眠は、脳のためにも、心のためにも、体のためにもとても大事なものです。
朝日を浴びて、体内時計をリセットする、よく噛んで食事をする、日中は無理のない範囲で動くように心がけるなど、できることから少しずつ取り入れてみましょう。
関連記事:脾虚とは 現代人は「脾」(ひ)が疲れてる!まずはここが整わないと、身体は整わない理由と漢方での整え方を徹底解説


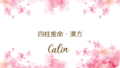

コメント